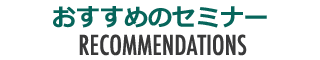会場受講/ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可)
第4期医療費適正化計画と


12月10日(水)
社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ 理事
よこすか地域包括ケア推進センター長
武藤 正樹(むとう まさき) 氏
第4期医療費適正化計画で後発医薬品の目標「2029年度までに全都道府県で80%以上」が導入された。しかし2025年9月の調査で後発品使用割合はすでに90%超、次なる目標の設定が必要だ。しかし後発医薬品の安定供給が依然として課題だ。後発品産業構造見直しについて見ていこう。さらに骨太の方針2025年に明記されたフォーミュラリーの普及についても見ていこう。
また、バイオシミラーの新目標は「80%置き換わったバイオシミラーの普及率が60%」だ。バイオシミラー普及を妨げる高額療養費制度などの5つのカベを見ていこう。
2025年の骨太の方針にOTC(一般用医薬品)が取り上げられた。なかでもスイッチOTCが課題だ。スイッチOTCの普及とその課題についても見ていこう。
1.医療費適正化計画とは?
2.第4期医療費適正化計画と後発品
・後発品90%時代
・後発医薬品の数量目標の見直しを
・後発医薬品の安定供給と産業構造の見直し
3.第4期医療費適正化計画とバイオシミラーの数値目標
・バイオシミラーの新目標
・バイオシミラーの普及の5つのカベ
・バイオシミラーの普及のための提言
4.都道府県地域フォーミュラリー導入
・骨太の方針とフォーミュラリー
・都道府県フォーミュラリーとは
・都道府県フォーミュラリーで後発品・バイオシミラーの普及を
5.セルフメディケーションとOTC医薬品
・OTC医薬品普及の提言
第5期医療費適正化計画にOTC医薬品の普及目標を
6.バイオシミラー、OTCの普及のための選択療養の導入を
7.質疑応答/名刺交換

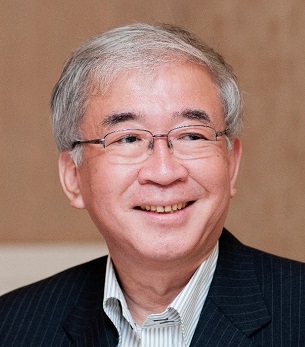
1949年3月8日生まれ 神奈川県出身。1974年4月新潟大学医学部卒業、1978年4月新潟大学大学院医科研究科修了後、同年より国立横浜病院にて外科医師として勤務。同病院在籍中厚生省から1986年?1988年までニューヨーク州立大学家庭医療学科に留学。1994年4月国立医療・病院管理研究所医療政策研究部長。1995年4月国立長野病院副院長。2006年4月より国際医療福祉大学三田病院副院長・同大学大学院医療経営福祉専攻教授、2020年7月より社会福祉法人日本伝道協会衣笠グループ相談役、2023年7月より理事。政府委員としては、医療計画見直し等検討会座長(厚労省2010年?2011年)、中医協入院医療等の調査評価分科会会長(厚労省2012年?2018年)、規制改革推進会議医療・介護ワーキンググループ専門委員(内閣府2019年〜2021年)、後発医薬品産業構造検討会座長(厚労省2023年〜2024年)、セルフケア・セルフメデイケーション推進に関する有識者検討会委員(厚労省2025年〜)。
【著書】
『2025年へのカウントダウン?地域医療構想と地域包括ケアはこうなる』(医学通信社2015年)、『ジェネリック医薬品の新たなロードマップ』(医学通信社2015年)、『医療と介護のクロスロード』(医学通信社2018年)、『医療介護の岩盤規制をぶっとばせ!: コロナ渦中の規制改革推進会議、2年間の記録』(篠原出版新社2021年)、『コロナで変わるかかりつけ医制度』(ぱる出版2022年)、『医療介護DX〜コロナデジタル敗戦からAIまで』(日本医学出版2023年)